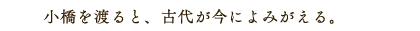
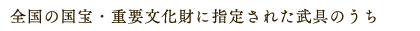


小橋を渡ると、古代が今によみがえる。
全国の国宝・重要文化財に
指定された武具のうち
8割が、ここ大山祇神社に所蔵されています。

宝物館 -宝物の紹介-
全国の国宝・国の重要文化財の指定を受けた武具類の約8割が、ここ大山祇神社宝物館に保存展示されています。甲冑の保存は全国一で、日本最古の平安中期の鎧をはじめ、鎌倉期~戦国時代まで各時代の代表する名品が展示されています。故に、当地大三島は「国宝の島」とよばれています。
鎌倉時代~南北朝時代の宝物
国宝 紫綾威鎧(むらさきあやおどしよろい)・大袖付(おおそでつき)
〈鎌倉時代 源頼朝奉納〉

鉄と革の平小札(ひらこざね)を一枚交(ま)ぜとし紫地小葵文綾(むらさきじこあおいもんあや)をもって威(おど)し、金具廻(かなぐまわり)・革所(かわどころ)は襷入獅子円文絵韋(たすきいりししまるもんえがわ)をもって包み、要所に金銅地板(こんどうじいた)を伏し車輪文金物(しゃりんもんかなもの)を打った荘重典雅(そうちょうてんが)な鎧で、鎌倉初期の典型的遺品である。綾威(あやおどし)の類例は極めて尠(すくな)く、厳島神社(いつくしまじんじゃ)の浅葱綾威鎧(あさぎあやおどしよろい)と当社の4領などが挙げられる。
重要文化財 長巻 銘 宗吉(ながまき めい むねよし)〈鎌倉時代〉
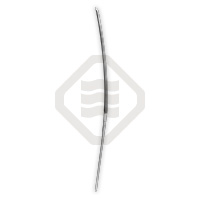
大太刀(おおだち)に茎(なかご)を継ぎ足して薙刀(なぎなた)として使用したものである。鎬造(しのぎづくり)で鍛えは板目(いため)流れ、刃文(はもん)は直刃調(すぐはちょう)の小乱(こみだれ)である。薙刀は上代(じょうだい)の鉾にかわって平安時代以後盛行した武器であるが、その遺品は少ない。このような鎌倉時代から南北朝時代にわたる古いものが、一括して伝存していることは珍しい。
国宝 大太刀 銘 貞治五年丙午千手院長吉(おおだち めい じょうじごねんへいごせんじゅいんながよし)
〈南北朝時代 後村上(ごむらかみ)天皇御奉納〉

鎬造(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね)、反り高く大鋒(おおきっさき)で、鍛えは板目柾(いためまさ)がかり、刃文(はもん)は小互(こぐ)の目に小乱交り(こみだれまじり)小沸(こにえ)つき、帽子尖り(ぼうしとがり)ごころに返る。表裏に丸留(まるどめ)の棒樋(ぼうひ)に連樋(つれひ)を彫る。茎(なかご)は生(う)ぶ。鑢勝手下り(やすりかってさがり)、佩裏(はきうら)に表記の銘がある。南北朝時代に流行した大太刀で何等(なんら)の破綻もなく出来の優れたしかも健全な名刀である。長吉は大和国千手院派(やまとのくにせんじゅいんは)の刀工(とうこう)。



